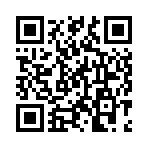2012年11月27日
奈良の春日野 3.
春日大社で参拝を済ませ、大社から西へ鬱蒼とした木立を抜け、飛火野へ向かいました。
ここまで来ると、修学旅行の喧騒も聞こえてきません。
途中、手の届くような至近距離で、母鹿が小鹿に乳を与えていました。

鹿、など草食動物は一様に、弱肉強食の習いからすると
「食べられる側」であり、食べられる側の動物は些細なことにも敏感であり
授乳、などは咄嗟のときに俊敏な動きが取れない無防備な行いであるにも関わらず
まさにこんな至近距離で子に乳を与える、というのは、よほど奈良の鹿は
人間に敵愾心はおろか、親近感さえもっているのであろうか、などと感動させられました。
これはおそらく人間が、鹿に対して悪意を持った行いをしない、ということは第一義ですが
さらに言うと、「しかせんべい」などという、コミュニケーション・ツールでもって
鹿を手なずけているからに他なりません。
この「しかせんべい」というツールは強力で
たとえば大仏殿前の参道などは観光客が多く
観光客が多い、ということは、鹿にとって絶好の「せんべいポイント」でもあるので
鹿の数も多くなるわけですが
ここで鹿せんべい、を、ひとくくり10枚、せんべい屋の露天のおばさんから購入しますと
それを見て取った鹿たちが、わらわらわらと、にじり寄ってきます。

「そのせんべいをわしにくれ」と、頭をさげて近づいてきます。
体にまだらのある小鹿ならまだしも、体毛がすっかり黒褐色になって老いさらばえた巨大ジカまで
のんのんのんと、首を上げ下げして近づいてきます。
近づいてくる、だけならまだしも、頭をみぞおちあたりにぶつけてきて
激しいせんべいコールを行います。
たまりかねて1枚、せんべいをあげると、

おおきにありがとう、わしにもくれ、わしもわしもとなって、しまいには逃げざるを得なくなります。

飛火野、は、奈良公園の南端にある青芝がまばゆい平原です。
春日大社の常緑樹からは、晩秋の木漏れ日が溢れています。

飛火野は、「とびひの」と読みます。
古い昔の古い言い伝えからついた名前ですが、趣のある地名です。
さだまさしの、まほろば、という歌の中にもこの地名が出てきます。
やや陰にこもった暗めの旋律の中に「春日山から飛火野あたり」というフレーズがありますが、
目のあたりの飛火野は、暮れなずむ空を背に、牧歌的ですらありました。

見晴らしの良い平原のそこかしこに、鹿が群れています。4、50頭はいるでしょうか。
どうやらここは、奈良公園の鹿たちの、ねぐらになっているようで
公園一帯に散らばっている鹿たちが、三々五々、帰還してきています。
凛、と澄み切った、もはや初冬を感じる張りつめた空気と、暮れなずむ空。
黙々と、草を食む鹿たち。
ベンチでくつろぐ、老夫婦。
静謐にして幽玄。
寂寞とした古都の夕暮れ。
ここで、しかせんべいを出してみます。

当然、くれ、と近寄ってきます。
ここにはせんべい売りのおばさんの露店もありません。
観光客の姿もほとんどありません。
鹿たちも、ここでせんべいをもらえる行幸に与れるとは思ってもいないでしょう。
数十頭の鹿が、うれしそうに首を振り振り近づいてきます。
すぐに半径5~6メートルの同心円内が、すべて鹿で満たされます。
鹿まみれ。
鹿三昧。
家へ帰ったら、飼い犬が飛んで逃げ、うなり声をあげました。
鹿臭かった、のだと思います。

ここまで来ると、修学旅行の喧騒も聞こえてきません。
途中、手の届くような至近距離で、母鹿が小鹿に乳を与えていました。

鹿、など草食動物は一様に、弱肉強食の習いからすると
「食べられる側」であり、食べられる側の動物は些細なことにも敏感であり
授乳、などは咄嗟のときに俊敏な動きが取れない無防備な行いであるにも関わらず
まさにこんな至近距離で子に乳を与える、というのは、よほど奈良の鹿は
人間に敵愾心はおろか、親近感さえもっているのであろうか、などと感動させられました。
これはおそらく人間が、鹿に対して悪意を持った行いをしない、ということは第一義ですが
さらに言うと、「しかせんべい」などという、コミュニケーション・ツールでもって
鹿を手なずけているからに他なりません。
この「しかせんべい」というツールは強力で
たとえば大仏殿前の参道などは観光客が多く
観光客が多い、ということは、鹿にとって絶好の「せんべいポイント」でもあるので
鹿の数も多くなるわけですが
ここで鹿せんべい、を、ひとくくり10枚、せんべい屋の露天のおばさんから購入しますと
それを見て取った鹿たちが、わらわらわらと、にじり寄ってきます。

「そのせんべいをわしにくれ」と、頭をさげて近づいてきます。
体にまだらのある小鹿ならまだしも、体毛がすっかり黒褐色になって老いさらばえた巨大ジカまで
のんのんのんと、首を上げ下げして近づいてきます。
近づいてくる、だけならまだしも、頭をみぞおちあたりにぶつけてきて
激しいせんべいコールを行います。
たまりかねて1枚、せんべいをあげると、

おおきにありがとう、わしにもくれ、わしもわしもとなって、しまいには逃げざるを得なくなります。

飛火野、は、奈良公園の南端にある青芝がまばゆい平原です。
春日大社の常緑樹からは、晩秋の木漏れ日が溢れています。

飛火野は、「とびひの」と読みます。
古い昔の古い言い伝えからついた名前ですが、趣のある地名です。
さだまさしの、まほろば、という歌の中にもこの地名が出てきます。
やや陰にこもった暗めの旋律の中に「春日山から飛火野あたり」というフレーズがありますが、
目のあたりの飛火野は、暮れなずむ空を背に、牧歌的ですらありました。

見晴らしの良い平原のそこかしこに、鹿が群れています。4、50頭はいるでしょうか。
どうやらここは、奈良公園の鹿たちの、ねぐらになっているようで
公園一帯に散らばっている鹿たちが、三々五々、帰還してきています。
凛、と澄み切った、もはや初冬を感じる張りつめた空気と、暮れなずむ空。
黙々と、草を食む鹿たち。
ベンチでくつろぐ、老夫婦。
静謐にして幽玄。
寂寞とした古都の夕暮れ。
ここで、しかせんべいを出してみます。

当然、くれ、と近寄ってきます。
ここにはせんべい売りのおばさんの露店もありません。
観光客の姿もほとんどありません。
鹿たちも、ここでせんべいをもらえる行幸に与れるとは思ってもいないでしょう。
数十頭の鹿が、うれしそうに首を振り振り近づいてきます。
すぐに半径5~6メートルの同心円内が、すべて鹿で満たされます。
鹿まみれ。
鹿三昧。
家へ帰ったら、飼い犬が飛んで逃げ、うなり声をあげました。
鹿臭かった、のだと思います。

2012年11月25日
奈良の春日野 2。
ヒサビサの奈良公園は、大勢の観光客で賑わっていました。
商店街を抜けて、興福寺の境内を通りました。
興福寺の五重の塔が、晩秋の青空に燦然と聳え立っています。

奈良は、景観条例で、この五重の塔よりも高い建造物を作ってはいけない、という
ことになっているらしい、ということを昔学生時代に、奈良に住む友人から
聞いたことがありました。
「上には建てられん。下を掘ったら遺跡が出てきて工事ストップや。
そんなんばっかりや。」友人がボヤいていたことを思い出しました。
広い境内の向こうは、きれいに手入れされた奈良公園が広がっていました。

つきぬけるような青空に、常緑樹の森。
大勢の観光客。そしてその中に、奈良公園なので当然ですが、鹿がいます。
東大寺における、神の使いであります。

観光客に混じって、鹿が悠然と歩いている、ということの不思議を感じます。

角は、ありませんでした。
そういえば駐車場から外へ出る途中、こんなポスターを見かけました。

どうやら、角は切られたて、のようです。
こんな看板もいたるところにありました。


奈良の鹿は基本おとなしいですがあくまで野生ですので
何があってもしりませんよ、という看板です。
しかも鹿はどうやらこの季節がいわゆる「ハッスル月間」のようで、
「ハッスル」が過ぎて気性も荒くなっているのでどうやら角を落とされる、みたいです。
東大寺に向かう参道にたむろする鹿たちは、皆一様におとなしく
観光客に頭をぽんぽん、とされても嫌がる気配すらありません。

長く広い参道を抜けると、目の前に東大寺大仏殿が広がりました。

蒼穹の空に映える、あおによし奈良の都の大仏殿。
あたりまえですが巨大、であります。
パンフレットによると758年建立で
それから焼き討ちにあったり台風で倒壊したりとっすったもんだがあって
今の伽藍は1709年再建、というのですが
今から300年以上前にこんなモノを作るとはやはりこの私たちの国ニッポンの物作りにかけての技術と情熱は、
などと感心させられます。
時節柄今がピークなのかも知れませんが、修学旅行の生徒の数が半端ではありません。

小学生、みたいです。
広島あるいは岡山弁、らしき「じゃけん」系のコトバが飛び交っています。

本殿脇で大勢の修学旅行の子供たちがカタマリになっているので
何があるのかと覗いてみると、柱に穴が開いていて、そこをくぐりぬけると何事かエンギが良い、ということで
ひとりづつ生徒がその穴をくぐっています。
くぐり抜けたところで先生が2人待ち構えていて、生徒を穴から引っ張り出して
上半身を出したところでVサインをする、ということを延々、くりかえしています。

穴を抜ける、だけならそんなに時間はかからないんでしょうが
出てきたところをいちいちカメラを構えてVサイン、をさせているので
列がなかなか進みません。順番待ちをしている生徒はおそらく100人以上いたようなので
1時間はかかるであろうなあ、なにもVサイン、をさせてまで撮る価値があるのか、
あの先生たちにとっては後々あるのであろうなあ。
退屈で半怪獣化した子供たちの嬌声歓声罵声が高天井の伽藍に共鳴反射して
うるさいのなんの。
早々に本殿を出て、お水取りで有名な二月堂へ向かいました。
ここも修学旅行の生徒たちに席巻されていましたが
大仏殿のような喧騒はありませんでした。

お堂へ続く石段を、ひとかたまりになって登っていく姿が
どこまでも続く青い青い空に溶け込んでゆきました。
続く(*^_^*)

商店街を抜けて、興福寺の境内を通りました。
興福寺の五重の塔が、晩秋の青空に燦然と聳え立っています。

奈良は、景観条例で、この五重の塔よりも高い建造物を作ってはいけない、という
ことになっているらしい、ということを昔学生時代に、奈良に住む友人から
聞いたことがありました。
「上には建てられん。下を掘ったら遺跡が出てきて工事ストップや。
そんなんばっかりや。」友人がボヤいていたことを思い出しました。
広い境内の向こうは、きれいに手入れされた奈良公園が広がっていました。

つきぬけるような青空に、常緑樹の森。
大勢の観光客。そしてその中に、奈良公園なので当然ですが、鹿がいます。
東大寺における、神の使いであります。

観光客に混じって、鹿が悠然と歩いている、ということの不思議を感じます。

角は、ありませんでした。
そういえば駐車場から外へ出る途中、こんなポスターを見かけました。

どうやら、角は切られたて、のようです。
こんな看板もいたるところにありました。


奈良の鹿は基本おとなしいですがあくまで野生ですので
何があってもしりませんよ、という看板です。
しかも鹿はどうやらこの季節がいわゆる「ハッスル月間」のようで、
「ハッスル」が過ぎて気性も荒くなっているのでどうやら角を落とされる、みたいです。
東大寺に向かう参道にたむろする鹿たちは、皆一様におとなしく
観光客に頭をぽんぽん、とされても嫌がる気配すらありません。

長く広い参道を抜けると、目の前に東大寺大仏殿が広がりました。

蒼穹の空に映える、あおによし奈良の都の大仏殿。
あたりまえですが巨大、であります。
パンフレットによると758年建立で
それから焼き討ちにあったり台風で倒壊したりとっすったもんだがあって
今の伽藍は1709年再建、というのですが
今から300年以上前にこんなモノを作るとはやはりこの私たちの国ニッポンの物作りにかけての技術と情熱は、
などと感心させられます。
時節柄今がピークなのかも知れませんが、修学旅行の生徒の数が半端ではありません。

小学生、みたいです。
広島あるいは岡山弁、らしき「じゃけん」系のコトバが飛び交っています。

本殿脇で大勢の修学旅行の子供たちがカタマリになっているので
何があるのかと覗いてみると、柱に穴が開いていて、そこをくぐりぬけると何事かエンギが良い、ということで
ひとりづつ生徒がその穴をくぐっています。
くぐり抜けたところで先生が2人待ち構えていて、生徒を穴から引っ張り出して
上半身を出したところでVサインをする、ということを延々、くりかえしています。

穴を抜ける、だけならそんなに時間はかからないんでしょうが
出てきたところをいちいちカメラを構えてVサイン、をさせているので
列がなかなか進みません。順番待ちをしている生徒はおそらく100人以上いたようなので
1時間はかかるであろうなあ、なにもVサイン、をさせてまで撮る価値があるのか、
あの先生たちにとっては後々あるのであろうなあ。
退屈で半怪獣化した子供たちの嬌声歓声罵声が高天井の伽藍に共鳴反射して
うるさいのなんの。
早々に本殿を出て、お水取りで有名な二月堂へ向かいました。
ここも修学旅行の生徒たちに席巻されていましたが
大仏殿のような喧騒はありませんでした。

お堂へ続く石段を、ひとかたまりになって登っていく姿が
どこまでも続く青い青い空に溶け込んでゆきました。
続く(*^_^*)

2012年11月23日
奈良の春日野。
奈良、に行ってきました。
この季節、京都に行ってきた、となると
清水やら神護寺やら、紅葉スポットがたくさんあって
「ああ、いいですねえ」となるんですが
「奈良に行ってきまして」と話すと、
「何しに?」という返事が大方の場合帰ってきます。

奈良は京都と並ぶ1000年の古都であり、
大仏さんはもちろんのこと、名所旧跡はひきもきらないのですが、
どうにも京都の陰に隠れてしまって、これという目的が無いと、
なかなか出かける機会がありません。
それでも私の記憶の中で、奈良へ行ったというのは
この10年間はお仕事がらみで出かけた程度で
あとは遥か昔々の小学校の修学旅行以来でありましたので、
ヒサビサに出かけてみよう、大仏さんのご尊顔も仰いで
鹿にせんべいのひとつもくれてやろう、と、休みの日に出かけました。
和歌山から阪和道、西名阪を通って法隆寺インターで降り
20分ほど北上して、奈良の市街地に入りました。
奈良も、街自体は大したことはありません。
和歌山と似たかよったか、といったところでしょうか。
しかしどこかリッパな街に見えるのは
奈良公園、という巨大な公園が広がり、その背後に青々とした
若草山が連なっているからでしょうか。

着いたのがお昼くらいだったので、お昼ごはんを食べに
近鉄奈良駅界隈の、一番の繁華街の「もちいどの商店街」付近を散策しました。
さて。ここでまた旅行者は考え込んでしまいます。
奈良に行って、これを食べねば、というモノがまったく思い浮かばないのです。
奈良漬けか、柿の葉ずしか、鹿せんべいくらいしか思い浮かばないのです。
これはどうしても押さえておきたい、といった食べ物が出てきません。
商店街は、賑わっていました。
客層が若いです。
和歌山の商店街、ぶらくり丁はもはや瀕死の状態ですが
こっちは駅チカ、大仏チカ、ということもあってか
地元の人や観光客で賑わっています。
とりあえず、せっかく奈良に来たことでもあるし
普段は食べられないモノを、ということで、ベトナム料理のお店をみつけて入りました。

奈良に来てベトナム料理もどうよ、と思いながらも
奈良漬を買って奈良公園のベンチでまるかぶりするわけにもいかず、
入ったこの「コムゴン」というお店はなかなかのスマッシュヒットでした。

注文を取りに来た40半ばの日本人女性がオーナーみたいでしたが
厨房の中はベトナム語らしきコトバが飛び交い
出てきた料理はなかなか見目も麗しく

味は、ベトナムへ行ったことがないのでわかりませんが日本人向けにすこし
妥協してくれているのか、スルスルおいしく頂きました。


近鉄奈良駅界隈の商店街でお昼をとってから
奈良公園に向かいました。
つづく(*^_^*)
この季節、京都に行ってきた、となると
清水やら神護寺やら、紅葉スポットがたくさんあって
「ああ、いいですねえ」となるんですが
「奈良に行ってきまして」と話すと、
「何しに?」という返事が大方の場合帰ってきます。

奈良は京都と並ぶ1000年の古都であり、
大仏さんはもちろんのこと、名所旧跡はひきもきらないのですが、
どうにも京都の陰に隠れてしまって、これという目的が無いと、
なかなか出かける機会がありません。
それでも私の記憶の中で、奈良へ行ったというのは
この10年間はお仕事がらみで出かけた程度で
あとは遥か昔々の小学校の修学旅行以来でありましたので、
ヒサビサに出かけてみよう、大仏さんのご尊顔も仰いで
鹿にせんべいのひとつもくれてやろう、と、休みの日に出かけました。
和歌山から阪和道、西名阪を通って法隆寺インターで降り
20分ほど北上して、奈良の市街地に入りました。
奈良も、街自体は大したことはありません。
和歌山と似たかよったか、といったところでしょうか。
しかしどこかリッパな街に見えるのは
奈良公園、という巨大な公園が広がり、その背後に青々とした
若草山が連なっているからでしょうか。

着いたのがお昼くらいだったので、お昼ごはんを食べに
近鉄奈良駅界隈の、一番の繁華街の「もちいどの商店街」付近を散策しました。
さて。ここでまた旅行者は考え込んでしまいます。
奈良に行って、これを食べねば、というモノがまったく思い浮かばないのです。
奈良漬けか、柿の葉ずしか、鹿せんべいくらいしか思い浮かばないのです。
これはどうしても押さえておきたい、といった食べ物が出てきません。
商店街は、賑わっていました。
客層が若いです。
和歌山の商店街、ぶらくり丁はもはや瀕死の状態ですが
こっちは駅チカ、大仏チカ、ということもあってか
地元の人や観光客で賑わっています。
とりあえず、せっかく奈良に来たことでもあるし
普段は食べられないモノを、ということで、ベトナム料理のお店をみつけて入りました。

奈良に来てベトナム料理もどうよ、と思いながらも
奈良漬を買って奈良公園のベンチでまるかぶりするわけにもいかず、
入ったこの「コムゴン」というお店はなかなかのスマッシュヒットでした。

注文を取りに来た40半ばの日本人女性がオーナーみたいでしたが
厨房の中はベトナム語らしきコトバが飛び交い
出てきた料理はなかなか見目も麗しく

味は、ベトナムへ行ったことがないのでわかりませんが日本人向けにすこし
妥協してくれているのか、スルスルおいしく頂きました。


近鉄奈良駅界隈の商店街でお昼をとってから
奈良公園に向かいました。
つづく(*^_^*)
2012年11月21日
LEDの商店街。
海南駅前一番街の、クリスマスイルミネーション。

今年で、もう10年目になります。
おじさんたちが集まって、一生けんめい飾り付け。

初めは白熱灯みたいな、黄色いチカチカ豆球だった飾りも、
最近は、ほとんどLEDになりました。


このペンギンは、20まんえん。
金額言ったらダメですね。
お子さんと一緒に写メ撮ってる人多数。
皆さん通りかかった時は、自転車なんかでぶつかってひっくり返さないでくださいね~
2時から装飾を初めて、終わった頃はいちめんの夕焼け。

海南駅前一番街のクリスマスイルミネーションは、12月25日まで。
お近くへお越しの際は、ぜひぜひ。


今年で、もう10年目になります。
おじさんたちが集まって、一生けんめい飾り付け。


初めは白熱灯みたいな、黄色いチカチカ豆球だった飾りも、
最近は、ほとんどLEDになりました。



このペンギンは、20まんえん。
金額言ったらダメですね。

お子さんと一緒に写メ撮ってる人多数。

皆さん通りかかった時は、自転車なんかでぶつかってひっくり返さないでくださいね~
2時から装飾を初めて、終わった頃はいちめんの夕焼け。

海南駅前一番街のクリスマスイルミネーションは、12月25日まで。
お近くへお越しの際は、ぜひぜひ。

2012年11月12日
ナビがむせぶ道・高野龍神 3。
高野龍神スカイラインは、高野山を北端に南下して
途中、和歌山県最高峰の護摩壇山を通り、
龍神温泉近くまで、和歌山県の背骨をあたりを
うねうねと走っています。
高野山で7分目だった紅葉は、標高を上げるごとに色づきを増していき、
旧花園村のアジサイ園の辺りからは、まさに見ごろ、となりました。

道路沿いは落葉樹が続き、黄色のトンネルの上方は蒼穹の空。
和歌山市内とはトーンが違う、ひとつ濃いめの青。
セルリアンブルーと群青色の中間の、蒼。
工場も排気ガスも無い、正しいニッポンの蒼空が広がっています。
申し訳ないほど、気分がいい
と、カーナビが突然、「奈良県に入りました」と言い、ナビの画像に大仏が映し出されました。
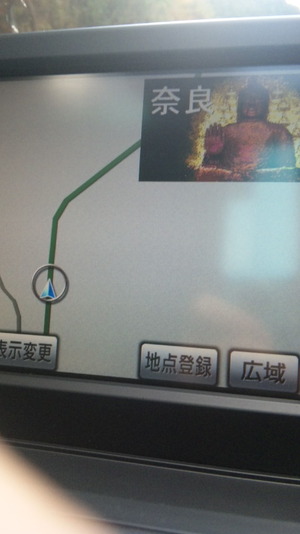
ぼくの車のカーナビは、府県境を超えると女性の声で高らかに、
○○県に、入りました。とアナウンスが入る、のは至極あたりまえかも知れませんが、
モニターに、その県の名所の写真まで表示される、妙なオプションがあります。
進行方向右手に、野迫川村、の案内標識が立っています。
「のせがわむら」と読むのであるなあ、と妙に感心して、さらに数百メートルも進んだでしょうか、
カーナビの女性がが再び、「和歌山県に、入りました」と言いました。
画面に、白浜の円月島が映し出されました。

またしばらく進むと、今度は「奈良県に、入りました。」と言いました。
画面には大仏が映っています。
時間にして、1分経ったか経っていないかです。
なるほど。と、ぼくは感心しました。
和歌山と奈良の県境の尾根に沿って走っているので
地理的にはどちらかの県の敷居を跨いでいる訳です。
ぼくは今までここを何度も走りましたが、前の車にはカーナビはついておらず、
カーナビ付きの車になって初めて、このスカイラインが和歌山と奈良を行きつ戻りつしているのだということに気がつきました。
しかしまあなんと律儀に、と感心する間もなく、
カーナビ嬢は「和歌山県に、入りました。」と言いました。
画面に円月島が映し出されました。
今度は20秒も経っていません。
すぐにまた切り替わって、大仏が映し出されました。
「奈良県に入りました」。
どうなっておるのか。
カーナビ嬢は単に地理的に本当に県境を厳密に衛星でつかまえて
一生けんめいアナウンスをしているだけなのですが
あまりにもめまぐるしいのです。
よく持って1分。
「和歌山県に、入りました」。
カーナビ嬢は叫び続けます。
あくまでも滑舌良く、明朗な、透き通る声です。
「奈良県に、入りました。」
奈良県に、で、一拍置くところに、
カーナビ嬢のこの仕事にかけるひたむきな情熱、のようなものを感じます。
一途な性格だと思います。
「和歌山県に、入りました。」
それから、護摩檀山のスカイタワーで一服するまで、
カーナビ嬢はけなげに、
奈良県に入りました和歌山県に入りましたを29回繰り返しました。
最後まで、大仕事をやり遂げました。
たおやかな声で、嫌な顔ひとつせずアナウンスをしてくれました。
今度時間ができたら一度ゆっくりガストでエスプレッソでも飲んで
この時の顛末を聞いてみたいと思います。

途中、和歌山県最高峰の護摩壇山を通り、
龍神温泉近くまで、和歌山県の背骨をあたりを
うねうねと走っています。
高野山で7分目だった紅葉は、標高を上げるごとに色づきを増していき、
旧花園村のアジサイ園の辺りからは、まさに見ごろ、となりました。

道路沿いは落葉樹が続き、黄色のトンネルの上方は蒼穹の空。
和歌山市内とはトーンが違う、ひとつ濃いめの青。
セルリアンブルーと群青色の中間の、蒼。
工場も排気ガスも無い、正しいニッポンの蒼空が広がっています。
申し訳ないほど、気分がいい

と、カーナビが突然、「奈良県に入りました」と言い、ナビの画像に大仏が映し出されました。
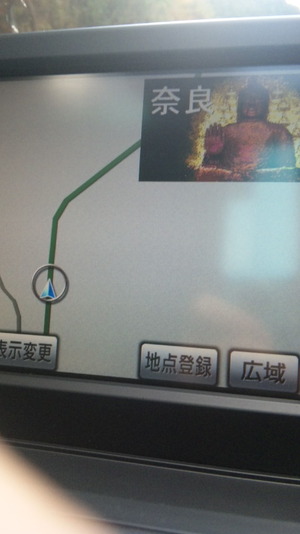
ぼくの車のカーナビは、府県境を超えると女性の声で高らかに、
○○県に、入りました。とアナウンスが入る、のは至極あたりまえかも知れませんが、
モニターに、その県の名所の写真まで表示される、妙なオプションがあります。
進行方向右手に、野迫川村、の案内標識が立っています。
「のせがわむら」と読むのであるなあ、と妙に感心して、さらに数百メートルも進んだでしょうか、
カーナビの女性がが再び、「和歌山県に、入りました」と言いました。
画面に、白浜の円月島が映し出されました。

またしばらく進むと、今度は「奈良県に、入りました。」と言いました。
画面には大仏が映っています。
時間にして、1分経ったか経っていないかです。
なるほど。と、ぼくは感心しました。
和歌山と奈良の県境の尾根に沿って走っているので
地理的にはどちらかの県の敷居を跨いでいる訳です。
ぼくは今までここを何度も走りましたが、前の車にはカーナビはついておらず、
カーナビ付きの車になって初めて、このスカイラインが和歌山と奈良を行きつ戻りつしているのだということに気がつきました。
しかしまあなんと律儀に、と感心する間もなく、
カーナビ嬢は「和歌山県に、入りました。」と言いました。
画面に円月島が映し出されました。
今度は20秒も経っていません。
すぐにまた切り替わって、大仏が映し出されました。
「奈良県に入りました」。
どうなっておるのか。
カーナビ嬢は単に地理的に本当に県境を厳密に衛星でつかまえて
一生けんめいアナウンスをしているだけなのですが
あまりにもめまぐるしいのです。
よく持って1分。
「和歌山県に、入りました」。
カーナビ嬢は叫び続けます。
あくまでも滑舌良く、明朗な、透き通る声です。
「奈良県に、入りました。」
奈良県に、で、一拍置くところに、
カーナビ嬢のこの仕事にかけるひたむきな情熱、のようなものを感じます。
一途な性格だと思います。
「和歌山県に、入りました。」
それから、護摩檀山のスカイタワーで一服するまで、
カーナビ嬢はけなげに、
奈良県に入りました和歌山県に入りましたを29回繰り返しました。
最後まで、大仕事をやり遂げました。
たおやかな声で、嫌な顔ひとつせずアナウンスをしてくれました。
今度時間ができたら一度ゆっくりガストでエスプレッソでも飲んで
この時の顛末を聞いてみたいと思います。

2012年11月11日
ナビがむせぶ道・高野龍神 2。
焼き餅で有名な花坂の集落を抜け、
急峻な道を駆け上がること20分。
目の前にいきなり大きな山門が現れました。
高野山の西の入り口、「大門」です。


大門を過ぎると、目の前に高野の町街が細長い帯状に数キロに渡って続きます。
高野山には117ものお寺があります。
お土産物屋や食堂はもちろん、
郵便局もあれば、紀陽銀行もあります。
人口も1万人近くあって、大学まである宗教都市です。
あれだけ急峻な山を登ってきて、目の前に忽然と、街が広がる様は、
ある意味カオスですらあります。
ちなみに、高野山、というのはあの辺り一帯の標高1000メートル前後のお山の集合体の総称で、
高野山、という名前の山は存在しない、そうです。
高野山の紅葉は、7分目、といったところでした。

寒かったです。
車についている外気温計は、12℃を指していました。

一番繁華な通りに、「森下商店」というごま豆腐で有名なお店があります。

ここの「生ごま豆腐」は、絶品です。
ごま豆腐、というと普通は少しきつね色、をしているものですが
完全無垢の純白で、舌触りがねっとり、というより、ぬっとり、として
口の中に入れた途端固形の体を成さず、淡雪のように、スーッと消えてなくなり
かすかなゴマの残り香だけが後から鼻腔を駆け抜けます。
高野山へ行かれた際には、ぜひともゲットしてください。

高野山街の東の外れの食堂できつねうどんを食べ、
いよいよ高野龍神スカイラインへ入って行きました。

つづく\(-o-)/
急峻な道を駆け上がること20分。
目の前にいきなり大きな山門が現れました。
高野山の西の入り口、「大門」です。


大門を過ぎると、目の前に高野の町街が細長い帯状に数キロに渡って続きます。
高野山には117ものお寺があります。
お土産物屋や食堂はもちろん、
郵便局もあれば、紀陽銀行もあります。
人口も1万人近くあって、大学まである宗教都市です。
あれだけ急峻な山を登ってきて、目の前に忽然と、街が広がる様は、
ある意味カオスですらあります。
ちなみに、高野山、というのはあの辺り一帯の標高1000メートル前後のお山の集合体の総称で、
高野山、という名前の山は存在しない、そうです。
高野山の紅葉は、7分目、といったところでした。

寒かったです。
車についている外気温計は、12℃を指していました。

一番繁華な通りに、「森下商店」というごま豆腐で有名なお店があります。

ここの「生ごま豆腐」は、絶品です。
ごま豆腐、というと普通は少しきつね色、をしているものですが
完全無垢の純白で、舌触りがねっとり、というより、ぬっとり、として
口の中に入れた途端固形の体を成さず、淡雪のように、スーッと消えてなくなり
かすかなゴマの残り香だけが後から鼻腔を駆け抜けます。
高野山へ行かれた際には、ぜひともゲットしてください。

高野山街の東の外れの食堂できつねうどんを食べ、
いよいよ高野龍神スカイラインへ入って行きました。

つづく\(-o-)/
2012年11月10日
ナビがむせぶ道・高野龍神。
紅葉の季節、がやってきました 。
。
和歌山市内はまだまだですが、東北や日光のあたりから紅葉の便りが届くころになると
和歌山では高野山や、高野龍神スカイラインが紅葉の見ごろを迎えます。
ちょうどテレビのニュースで、日光中禅寺湖の紅葉が今真っ盛り、というニュースが流れたので
たまの休日、晴天、気温18度という誠に良いお日柄でもあり
車で高野龍神スカイラインへ向かいました 。
。
高野龍神スカイラインは、和歌山県と奈良県の県境の紀伊山地を
山の尾根に沿って走る見晴らしバツグンの道で
かつては有料でありました。
北の入口は高野山から南へ少し走ったところにあって
スカイラインの入口で、道ができた当時、確か1000円ほど取られたキオクがあります。
1000円は高いなあ、と思いながらも、花園のアジサイ園の辺りから、
右手には和歌山県の、海に向かってやや標高を下げるかのような重畳としたやさしい山並みを、
左手には奈良県の、さらに険しさを増す山塊を眺めながら走っているうちに誠に爽快な気分になるんですが 、
、
数十キロ走って終点になるとまた今度は出口ゲートで1000円ほど取られて眉間に縦ジワが入る 、という
、という
やや、お高いロードでありました。
今では償却期間が終わって、無料で絶景を堪能することができるオススメドライブルートです。
和歌山市を出て50分ほど、紀ノ川を遡上するように、東へ東へと走ります。
市街地を抜け、刈り取られた田んぼや、
二つ三つ実を残して枝だけになった柿の木などが心を和ませてくれます 。
。
やがて紀ノ川の流れが少し狭隘になると、突如、鬱蒼とした木々に囲まれた大きな中州が現れ、
紀ノ川は二股に分断されます。
この中州は「へび島」と言います。
なんともおどろの名前なのですが、
こんもりとした中州の森は、本名を「船岡山」と言い、
中には広島と同じ名前の「厳島神社」というお社があるらしいです。

ありがたい中州なのですが、子供の頃助手席からこの島を眺めていると、
実際に蛇が岸から中州へ、あるいは中州から岸へ向かって
あきらかにそれしかない水紋を描きながら泳ぎ渡っているのを目撃したことがあるので
恐らくあの森の中では蛇がとぐろを巻いているのではないだろうか、と、未だに想像をさせられます。
この中州を過ぎて、国道を右に曲がり南下すると、道は山間になります。
焼き餅で有名な花坂、という集落を過ぎると、道は急峻になり、高野山へと駆け上ります。
続く\(-o-)/
 。
。和歌山市内はまだまだですが、東北や日光のあたりから紅葉の便りが届くころになると
和歌山では高野山や、高野龍神スカイラインが紅葉の見ごろを迎えます。
ちょうどテレビのニュースで、日光中禅寺湖の紅葉が今真っ盛り、というニュースが流れたので
たまの休日、晴天、気温18度という誠に良いお日柄でもあり
車で高野龍神スカイラインへ向かいました
 。
。高野龍神スカイラインは、和歌山県と奈良県の県境の紀伊山地を
山の尾根に沿って走る見晴らしバツグンの道で
かつては有料でありました。
北の入口は高野山から南へ少し走ったところにあって
スカイラインの入口で、道ができた当時、確か1000円ほど取られたキオクがあります。
1000円は高いなあ、と思いながらも、花園のアジサイ園の辺りから、
右手には和歌山県の、海に向かってやや標高を下げるかのような重畳としたやさしい山並みを、
左手には奈良県の、さらに険しさを増す山塊を眺めながら走っているうちに誠に爽快な気分になるんですが
 、
、数十キロ走って終点になるとまた今度は出口ゲートで1000円ほど取られて眉間に縦ジワが入る
 、という
、というやや、お高いロードでありました。
今では償却期間が終わって、無料で絶景を堪能することができるオススメドライブルートです。
和歌山市を出て50分ほど、紀ノ川を遡上するように、東へ東へと走ります。
市街地を抜け、刈り取られた田んぼや、
二つ三つ実を残して枝だけになった柿の木などが心を和ませてくれます
 。
。やがて紀ノ川の流れが少し狭隘になると、突如、鬱蒼とした木々に囲まれた大きな中州が現れ、
紀ノ川は二股に分断されます。
この中州は「へび島」と言います。
なんともおどろの名前なのですが、
こんもりとした中州の森は、本名を「船岡山」と言い、
中には広島と同じ名前の「厳島神社」というお社があるらしいです。

ありがたい中州なのですが、子供の頃助手席からこの島を眺めていると、
実際に蛇が岸から中州へ、あるいは中州から岸へ向かって
あきらかにそれしかない水紋を描きながら泳ぎ渡っているのを目撃したことがあるので
恐らくあの森の中では蛇がとぐろを巻いているのではないだろうか、と、未だに想像をさせられます。
この中州を過ぎて、国道を右に曲がり南下すると、道は山間になります。
焼き餅で有名な花坂、という集落を過ぎると、道は急峻になり、高野山へと駆け上ります。
続く\(-o-)/